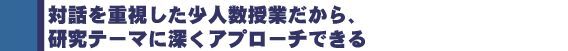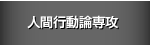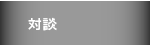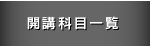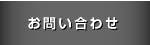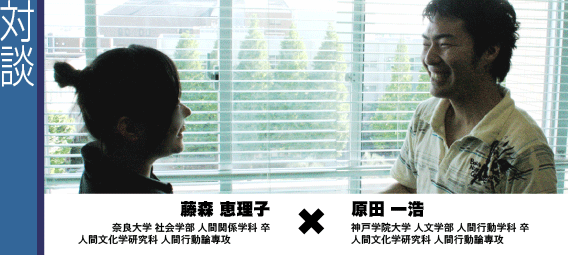
| 原田: | ぼくが人間文化学研究科に進学したのは、人文学部で発達心理学を中心に学んでいたのですが、いろいろとやっていくうちに社会心理学に興味を持つようになり、社会心理学についてもう一度深く学びたいと思ったからです。藤森さんは、どんなきっかけで進学を決めたんですか? |
| 藤森: | 私は学外からの進学で、大学のときには、正月や七五三などの慣習としての宗教について社会心理学からのアプローチをしていました。大学院でも心理学を学ぼうかとも思ったのですが、他の分野からも慣習的な宗教に対しアプローチしたいと考えました。そこで、教育学にとらわれすぎていない、神戸学院大学の人間文化学研究科を選びました。今は、日本のなかで宗教がどういう位置づけかを自分の中で明確にするため、明治憲法と日本国憲法の制定の背後について調べています。 |
| 原田: | 自分のテーマに向けて、もうすでに研究をはじめているんですね。研究も学部よりも本格的になる一方で、大学院の授業も密度が濃いですよね。大学院の授業は少人数ですから、一時も気が抜けない。予習も復習もやっていて当たり前です。 |
| 藤森: | そうそう。私の場合、原田くんと一緒に受けている「東洋人と西洋人の比較」について書かれた文献を読み解いて発表する授業が、とくに大変です。みんなひとりで90分授業一回じゃ終わらないぐらい中身の濃い発表をするから、私も発表の順番がまわってくる前の週はまるまる一週間を使って準備をしています。本を読んでわからないところに付箋をして、そこを調べてまた本を読み直す。それにレジュメも制作しなくてはいけないし。毎日が学問との格闘で、スリリングですね。 |
| 原田: | 学部との違いという意味では、ワークショップ形式の授業が増えたことも印象的です。とくに臨床心理学の授業で二人一組になって、片方が目をつぶり、もう片方が相手の手を引っ張って学内を歩く授業が強く記憶に残っています。これは信頼関係を目的にしたワークショップで、信頼関係を築くことの大切さを学びました。 |
−−先生や先輩との会話が研究の励みになる。
| 原田: | 大学院の授業で一番特徴的なものと言えば、やっぱり演習。ぼくのとっている演習は、英語で書かれた心理学の文献を読み解いて発表することを中心にやっています。1人の担当ページが30ページほどあって、それを読んで翻訳するのですが、むずかしい専門用語が多くて、理解するのにかなり時間がかかります。 |
| 藤森: | 私の受けている演習は少し形式が違いますね。ドクターの先輩二人と私の三人でやっていて、人数が少ないこともあり先生との「対話」を中心に授業が進んでいきます。演習のテーマも、死とは何かとか、武士道とは何かといった、どちらかというと抽象的なテーマが多いので、じっくり話し合うスタイルに授業内容がよく合っているような気がします。 また演習以外でも、私のとっている授業は人数が少ないものが多くて、受講生が私一人だけというのも多くあります。マンツーマンだと、こっちがわからないとすぐに気づいてもらえるので理解も深まるし、気が抜けないため授業にハリがあります。 |
| 原田: | 藤森さんの演習のようにドクターの先輩と一緒の授業を受けていると、いいアドバイスをもらえたりすることもあるんじゃないですか?それに授業にでなくても、同じ院生研究室を使っていたりすると話し合う機会がけっこうあったりする。この前、心理学について先輩と語っていたら、その知識量の多さに圧倒されてしまった(笑) |
| 藤森: | 院生たち数人ごとに割り当てられる院生研究室。あれは先輩と後輩が入り乱れていて部室みたいな感じで、すごくリラックスできますね。私の研究している「人間形成論」の分野はあまり人数が多くありませんが、ドクターの先輩と先生の仲がいいから、昼休みになると先生がやってきて一緒にごはんを食べることもあって。何気ない日常のなかででも、学術的な会話ができるのが魅力です。 |
−−それぞれの研究テーマ。
| 原田: | 先ほど少しだけ会話に出てきたけど、藤森さんは研究テーマをもうすでに決めているの? |
| 藤森: | 教育学の視点から宗教を考えることは決めているけど、まだ具体的なテーマは見えていません。いろいろな先生に話しを伺ってみたら、みんな自分の専門からのアプローチを教えてくれて。どれも魅力的だけど、そのせいもあり返って一つに絞り込めないんです。 |
| 原田: | なるほど。ぼくはリスクコミュニケーションをテーマにしようとは考えているけど、知識が足りず文献をあさっている状態。 |
| 藤森: | リスクコミュニケーション? |
| 原田: | 例えば、商品の説明をする時に、メリットばかり提示するのではなく、その商品のリスクについても提示しようというものでそうした説明の方が信頼性はあがる。これは最近の風潮として、情報の「公平さ」を求めるようになってきた考え方で、この新しい研究分野にやりがいを感じています。 |
−−集中して学べる環境を最大限に利用する。
| 原田: | 人間文化学研究科に入って、学部生のうちにやっておいた方がよかったこと、また逆にやっておいて役立ったことってありますか?ぼくの場合は発達心理学から社会心理学に転向してきたこともあって、大学のうちに専門知識をある程度、養っておく大切さを痛感しました。あとそれに語学ですね。研究が専門的なっていくと、英語で書かれた文献を読む機会もかなり増えていきます。どんな研究でもそうですけど、語学力、とくに英語での読解力は必要だと感じています。 |
| 藤森: | 他大学から編入してきた私としては、入学する前に大学のイメージを勝手に作り出したりせずに入学することが大事だと感じました。あまり先入観を持ちすぎると大学に入った後、馴染みにくくなると思うので。私はそういうのが一切なかったから、すんなりみんなと仲良くなれました。あとは先生と学生の距離が学部のときに比べてグンと近くなるし、集中して学べる環境が整っているので、最大限にそれを利用できるよう何事にも意欲的に取り組んでいくことが必要。私自身、意欲的に活動しているつもりではいるんですが、これからはもっと努力していきたいですね。 |