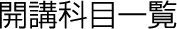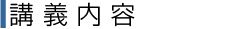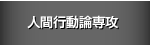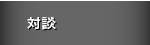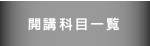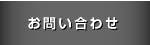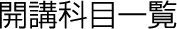
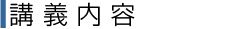
- 研究指導
- 春日 雅司
- 教育目標
- 現在、 わが国では 「格差」 という言葉が氾濫しています。 それがどういう意味でどのような事項に対して使われるものであるかはとても重要なことです。 たとえば 「地域格差」 という言葉はよく聞きますが、 この地域がいったいどういう範囲を指すのか、 都道府県なのか市町村なのか、 あるいはもっと狭い範囲なのかが分かりません。 使っているのは政治家が多いようで、 恐らく 「都鄙」 について言っているのでしょうが、 決して明確ではありません。 また格差は何についてなのか、 恐らく 「経済的」 に測定できる数値のようなものを考えているのでしょうが、 「政治的」 なものもあれば 「文化的」 ・ 「社会的」 なものも量化できるわけで、 一体何なのか不明確です。 このように、 われわれが生活している現代社会において、 ある事象を表現しようとすると、 概念はとても大切なものとして断ち現れてきます。 この授業は、 地域社会の活性化をテーマにしていますが、 「地域」 とは何か、 また 「社会」 や 「活性化」 とは何かと考えてると、 果てしなく続く砂漠のようにも思えますが、 大学院で勉強していくということは、 このような疑問に一つ一つ答えていくことです。 しかも、 一つ一つきちんと定義づけられていると同時に全体としてのバランスも必要です。
授業では 「地域社会の活性化」 をテーマに、 地域社会や社会運動に関する学説を理解しまとめるとともに地域商店街や地場産業の活性化の具体的事例研究を通じて、 論文のとりまとめを行っていきます。 博士論文作成に向けて、 学生の問題意識をより明確にし、 それを具体的かつ体系的に方向づけながら、 必要なスキルをさらに習得すると共に投稿論文としてまとめていけるようにしたいと思います。 その際、 全体構想の特に前半部分にあたる学説部分を中心に文献読解を進めていきますが、 学生は教員の指導のもと後半部分の実証的研究を進めながら学説研究にあたってください。 また、 修得した調査スキルを利用して、 分権サーベイだけでなく現実の地域社会におけるさまざまな調査も進めてください。
- 授業内容
- 授業は社会運動や資源動員論に関する内外の文献の購読を行います。 受講者は論文作成に必要な論文・文献・資料などを順次読み進め、 レジュメを作成し報告するという作業を続けていきます。 また実証に必要な資料・データなどは授業の中で受講生に指示するので、 その指示にしたがって作業を進めていただき、 適宜報告するという形にしたい。 そのため、 テーマの性質上、 授業時間以外に地域に出かけて行って聞いたり調べたりする仕事があることを了承していただきたい。
▲このページのトップへ
- 研究指導
- 神原 文子
- 教育目標
- 本年度の研究指導では、 毎回、 ゼミ形式で行い、 すべての院生が、 研究テーマについて研究報告を行うことを原則とする。 ただし、 必要に応じて、 研究方法、 実証研究方法、 文献レビュー等も組み込む予定である。院生には、 1年間に最低1本、 できれば2本の論文を完成させて、 いずれかの学術雑誌に投稿することを期待する。
- 授業内容
- 前期は、 以下のような社会学プロセスを具体的に行うことを中心とする。
①原問題──研究テーマを決める。 テーマが決まらなければ、 関心のある事柄、 疑問を抱いている事柄、 調べてみたい事柄などを書き出してみることから始める。
②関連文献の見直しと既存研究の検討──研究テーマに関連した文献や既存研究を検討するいわば 「外部探検」 のプロセスである。
③問題意識の確定──自分が関心をもった現実を粗く素描する。
④戦略的な問題規定──実証の対象にどれだけなりうるか、 最小限明らかにすべき課題はどの部分なのかを限定づける。
⑤概念分析──問題を作り上げている主要な事柄 (要素項目) を言葉で記述し、 対象となっている事象の全体像を描くことである。
⑥理論仮説──理屈のうえで、 要素や属性を相互に関連づける手続きである。
⑦作業仮説──概念から測定可能な変数を作成し、 変数相互の関連づけを行う。
後期は、 各自のテーマについて、 研究発表を行う。
▲このページのトップへ
- 研究指導
- 寺嶋 秀明
- 教育目標
- 博士論文の準備と作成
- 授業内容
- まず研究テーマについてであるが、さまざまな情報収集、文献の渉猟をおこない、学生との対話やを介して多くの方面から議論を深め、適切なテーマを設定する。つぎに資料収集のためのフィールドワークの立案と実行、収集資料の整理と分析、それらを利用した研究発表等についての指導と討論をおこない、研究を深めてゆく。最終的には博士論文の完成へ向けて指導をおこなう。
▲このページのトップへ
- 研究指導
- 二杉 茂
- 教育目標
- 博士論文の完成に向けてのトレーニング及びサポート
- 授業内容
- ① 研究デザインの点検
② 既執筆部分の内容点検
③ 現在の執筆状況の確認
以上の要点を格に、論理性、独創性、説得力を踏まえたロジックの構築をめざす。
▲このページのトップへ
- 研究指導
- 前林 清和
- 教育目標
- 博士論文に向けての研究
- 授業内容
- 1 「研究デザインの確認と精査」
2 「公刊論文の検討」
3 「研究方法の指導」
4 「調査に関する指導と実施」
5 「論文執筆の指導」
▲このページのトップへ
- 研究指導
- 山鳥 重
- 教育目標
- 博士論文に値する研究遂行を援助
- 授業内容
- 学生が、現場での診療・治療の過程で抽出した高次脳機能障害の臨床的症状について、その臨床的価値、神経解剖生理学的位置づけ、病態メカニズムの理解、病態解明に向けての研究方法、などについて指導する。
▲このページのトップへ
- 研究指導
- 早木 仁成
- 教育目標
- 主に霊長類社会学に関する分野の研究を進め、 学位論文の作成を目指す
- 授業内容
- 霊長類の社会と行動に関するフィールドワークにもとづいて、 データの収集と分析を進め、 人類の進化過程の解明にかかわる博士論文の作成を目指して研究指導を行う。
まず、 博士論文作成のための文献収集、 問題設定、 目的の設定、 仮説の設定、 フィールドワークでのデータ収集の方法を確実に身につける。 また、 自らの研究を追究する道筋を明確にし、 研究の位置づけや、 研究方法の妥当性を検討し、 データの分析方法を学ぶ。 その上で、 関連する重要な文献を読みながら、 研究結果に関する発表と討論を繰り返す。
▲このページのトップへ
- 研究指導
- 小石 寛文
- 教育目標
- 学位論文に向けての研究指導
- 授業内容
- 学位論文のための研究を進めていくために、 先行研究の文献研究から自分の研究を位置づけ深めること、 全体の研究の構想、 研究方法の吟味、 データ処理法など学位論文執筆に必要なことを指導する。 そのために、 受講者は毎回自分の研究の進捗状況や今後の進め方について報告し、 それにもとづいて指導支援する。
▲このページのトップへ
- 研究指導
- 水本 浩典
- 教育目標
- 博士論文へのアプローチ
現在博士後期課程に在学中の学生がそれぞれ設定している研究テーマの具現化=論文化について、 適宜、 問題点の指摘や方法論へのアドバイスを通じて自分自身の主張を持った論文に具現化する過程を指導する。
- 授業内容
- 博士後期課程在学中の学生が自分自身で設定するテーマについて、 毎週、 担当者を決めて現在進行中の論文作成過程について発表させる。 授業メンバーとともに、 論文へのアプローチの合評を行う。
その過程で、 アプローチの方法についてのアドバイスを適宜交えながら、 問題点と研究へのアプローチ手法、 結論への誘導などについて指導を行っていく。
▲このページのトップへ