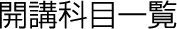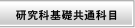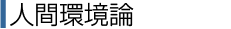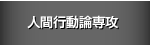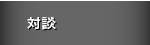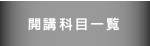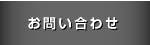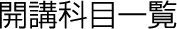
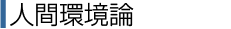
人間環境論方法論 I
五 島 喜與太
- 教育目標
- 自然環境の仕組みと人間の関わり
- 授業内容
- 環境論は本来、自然環境論と置き換えて良いくらい、研究対象としては我々を取り巻く自然環境の仕組みや変化を論じる分野であった。しかるに今日、環境と人間との結びつきは極めて密接となり、例えば、地球環境に優しくとか環境破壊などの言葉が日常的に用いられる。環境との結びつきを論じない人間論はなく、また逆に人間を抜きにした環境論もない。
しかしながら、人間と環境を 「人間環境論」 とひと括りをした途端にこれを研究する切り口は容易に見あたらない。人間を主役とするか自然環境を守るかでは、アプローチにかなりの開きが生じる。
ここでは、まず自然環境の仕組みやその変化の幾つかを取り上げ、人間が制御できる部分とできない部分について考察し、制御可能性の範囲をいかにして拡大しうるかを考える。
▲このページのトップへ
人間環境論方法論 II
五島 喜與太
- 教育目標
- バイオ技術と生老病死
- 授業内容
- 20世紀中頃から生命科学分野はすさまじいという表現がふさわしい発展をしてきました。
| 1944年 | : | 「遺伝子の本体=DNA」 |
| 1953年 | : | 「DNA 二重らせんモデル」 |
| 1974年 | : | 「遺伝子組換え技術」 |
| 1970年〜 | : | 「がんなどの遺伝子病の発見」 |
| 1944年 | : | 「DNA 診断、遺伝子治療」 |
| 1944年 | : | 「体外受精技術の進歩」 |
| 1944年 | : | 「臓器移植、再生医療」 |
| 1997年 | : | 「クローン羊誕生」 |
| 1998年 | : | 「ヒト ES 細胞の培養に成功」 |
- これらの発展の影響は単に生命科学の分野に留まらず、私たちの日常生活、医療環境、生命観、文化にも大きな影響を与えつつあります。
この講義では、生命科学の世界を学び、そこからなにが生まれてくるのかについて探り、考えたいと思っています。
▲このページのトップへ
人間環境論特殊講義 I
森田 茂
- 教育目標
- 障害者と環境
- 授業内容
- 社会福祉の理念として、リハビリテーションおよびノーマライゼーションが両輪のように掲げられることがある。能力や権利の回復を語義とするリハビリテーションは自立概念を基調とし、非人間的処遇に対する抵抗を背景とするノーマライゼーションは共生概念に通じる。これらから、エンパワメント、バリアフリー、インクルージョン等の新たな理念や方法が編み出されている。障害者の福祉を考える場合、この様な福祉理念に対する考察と共に、障害とは何かについての認識を深める必要がある。
障害者の生活は、さまざまな社会的障壁のために不利を被ることが多いことを否定できない。このことは、障害者を一人の人間として認識をする前にその 「障害」 のみを意識しがちであることから偏見や差別を生み出し、また、その 「障害」 を個人レベルの問題としがちであることから、社会的責任が不明確になりやすいことによってもたらされる。
障害者の社会参加を阻む障害になるとして、制度的、物理的、情報・文化的、意識的な各面から種々の問題の解決法を考察し、社会的方策を考えていきたい。
▲このページのトップへ
人間環境論特殊講義 II
大塚 成昭
- 教育目標
- 地球システムとしての地球環境の理解
- 授業内容
- 地球は、地殻・マントル・核からなる 「固体地球圏」、大気・海洋からなる 「流体地球圏」、その外の宇宙空間に広がる 「地球磁気圏」 によって構成されている。これらの地球を構成する要素は、その内部および相互間でエネルギーや物質が絶えず移動・交換されており、互いに影響を及ぼしあっている。すなわち、一つのシステムとして捉える必要がある。ここでは、地球システム論の観点から人間環境の基礎としての地球環境について講義する。以下の項目について、13回で講義するとともに、適宜、課題を提示してレポートを提出してもらう予定である。
1. 地球システムについて
2. 地球における物質循環
3. 地球におけるエネルギーの流れ
4. 地球システムの安定性と気候変動
5. 地球環境論における諸問題
▲このページのトップへ
人間環境論演習 I(E)
大塚 成昭
- 教育目標
- 人間環境に関する研究課題の発見
- 授業内容
- この演習 I では、地球科学に関する学術雑誌に掲載された論文を読むことによって地球科学、災害科学、地球環境問題などに関する知識を広げながら、同時に学生諸君の研究課題を見つけるように指導する。受講者は、自分の関心のあるテーマについて文献調査などを行い、その成果を発表する。また、場合によっては、野外調査、実験なども実施する。
授業は、この学生諸君の発表と討論を中心に行う。
| 第1回 | 基本方針の確認と課題提示 |
| 第2回〜第12回 | 学生諸君の報告と議論 |
| 第13回 | まとめ |
▲このページのトップへ
人間環境論演習 I(B)
五島 喜與太
- 教育目標
- 人間生活と環境 I
- 授業内容
- 20世紀の大量生産・大量消費・大量廃棄が生み出した地球規模から身近な生活に至る人間環境の変化、科学技術とりわけ生命科学の進歩による私たちの医療環境の変化、さらに、コンピューターの進歩と普及がもたらした情報環境の変化など、めまぐるしく変容していく社会に私たちは生きています。本学の図書館所蔵の雑誌などには、これらの問題についての最新の情報が掲載されています。この演習では、その中から受講生各自が興味をもった文献を紹介し、私も含めて受講生全員による質疑応答、討論を通して、それらの問題への理解を深めていきます。
▲このページのトップへ
人間環境論演習 I(H)
藤井 一成
- 教育目標
- 環境変化と体力問題
- 授業内容
- 社会の変化、生活環境の変化が子供たちの体力・運動能力に悪影響を及ぼしている。なぜそうなったのかを問題にし、調査研究してその成果などを討論していく。
▲このページのトップへ
人間環境論演習 II(E)
大塚 成昭
- 教育目標
- 人間環境に関する研究課題の発見 (続)
- 授業内容
- この演習Ⅱでは、 演習Ⅰに続いて地球科学に関する学術雑誌に掲載された論文を輪読することによって地球科学、 災害科学、 地球環境問題などに関する知識を広げながら、 同時に学生諸君の研究課題を見つけるように指導する。 受講者は、 自分の関心のあるテーマについて文献調査などを行い、 その成果を発表する。
また、 場合によっては、 野外調査、 実験なども実施する。
授業は、 この学生諸君の発表と討論を中心に行う。
第1回 基本方針の確認と課題提示
第2回〜第12回 学生諸君の報告と議論
第13回 まとめ
▲このページのトップへ
人間環境論演習 II(B)
五島 喜與太
- 教育目標
- 人間生活と環境 II
- 授業内容
- 20世紀の大量生産・大量消費・大量廃棄が生み出した地球規模から身近な生活に至る人間環境の変化、科学技術とりわけ生命科学の進歩による私たちの医療環境の変化、さらに、コンピュータの進歩と普及がもたらした情報環境の変化など、めまぐるしく変容していく社会に私たちは生きています。本学の図書館所蔵の雑誌などには、これらの問題についての最新の情報が掲載されています。この演習では、その中から受講生各自が興味をもった文献を紹介し、私も含めて受講生全員による質疑応答、討論を通して、それらの問題への理解を深めていきます。
▲このページのトップへ
人間環境論演習 II(H)
森田 茂
- 教育目標
- 身体障害者スポーツとボランティア
- 授業内容
- 障害者スポーツという特殊なスポーツがあるわけではない。みんなが親しんでいるスポーツのルールに少し工夫をして行っているだけである。この様に考える時、障害者の親しめるスポーツには、子供や高齢者にも通じるものであり、誰にでも出来るものである。したがって、スポーツをみんなのものとして、障害を受けている人達をスポーツの場に誘い出してくれるような、いわば、障害者にスポーツへの動機付けをしてくれ人達が、一人でも多く求められている。
障害者だけでなく誰にでも出来るスポーツの考案やルールの改正および障害者スポーツ指導員の育成の強化策などを考えていきたい。
▲このページのトップへ
人間環境論演習 III(E)
大塚 成昭
- 教育目標
- 人間環境に関する研究課題の追究
- 授業内容
- この演習 III を履修する時点では、受講生諸君は修士論文研究課題を見つけているはずである。受講者は、各自が定めた研究課題に関連する文献調査、野外 (実地) 調査、観測などテーマに合わせて種々の資料収集、分析、考察等を行い、その成果を発表する。
演習㈵と同様に、授業は、学生諸君の発表と討論を中心に行う。これを通して、修士論文の内容充実を目指す。
| 第1回 | 基本方針の確認と課題提示 |
| 第2回〜第12回 | 学生諸君の報告と議論 |
| 第13回 | まとめ |
▲このページのトップへ
人間環境論演習 III(B)
五島 喜與太
- 教育目標
- 人間生活と環境 III
- 授業内容
- 20世紀の大量生産・大量消費・大量廃棄が生み出した地球規模から身近な生活に至る人間環境の変化、科学技術とりわけ生命科学の進歩による私たちの医療環境の変化、さらに、コンピュータの進歩と普及がもたらした情報環境の変化など、めまぐるしく変容していく社会に私たちは生きています。本学の図書館所蔵の雑誌などには、これらの問題についての最新の情報が掲載されています。この演習では、その中から受講生各自が興味をもった文献を紹介し、私も含めて受講生全員による質疑応答、討論を通して、それらの問題への理解を深めていきます。
▲このページのトップへ
人間環境論演習 III(H)
藤井 一成
- 教育目標
- アウトドアスポーツと環境問題
- 授業内容
- 地球環境に対する危機感が世界中で高まっている。
そんな中、 アウトドアスポーツは環境問題とどのように関わっているのか、 その問題点をさぐる。 特にゴルフ・スキー・マリンスポーツについて調査研究をすすめていく。
この授業は、 学生の発表と討論を中心に行う
第1回 ガイダンス
授業の進め方、 評価について
第2回〜12回 プレゼンテーション
発表と討論
第13回 まとめ
まとめと総括
▲このページのトップへ
人間環境論演習 IV(E)
大塚 成昭
- 教育目標
- 人間環境に関する研究課題の追究 (続)
- 授業内容
- 演習Ⅲに引き続き、 この演習Ⅳでは、 各自が定めた研究課題に関連する文献調査、 野外 (実地) 調査、 観測などテーマに合わせて種々の資料収集・分析・考察等を行い、 その成果を発表する。
演習Ⅲと同様に、 授業は、 学生諸君の発表と討論を中心に行う。 これを通して、 修士論文の内容充実を目指す。
第1回 基本方針の確認と課題提示
第2回〜第12回 学生諸君の報告と議論
第13回 まとめ
▲このページのトップへ
人間環境論演習 IV(B)
五島 喜與太
- 教育目標
- 人間生活と環境 IV
- 授業内容
- 20世紀の大量生産・大量消費・大量廃棄が生み出した地球規模から身近な生活に至る人間環境の変化、科学技術とりわけ生命科学の進歩による私たちの医療環境の変化、さらに、コンピュータの進歩と普及がもたらした情報環境の変化など、めまぐるしく変容していく社会に私たちは生きています。本学の図書館所蔵の雑誌などには、これらの問題についての最新の情報が掲載されています。この演習では、その中から受講生各自が興味をもった文献を紹介し、私も含めて受講生全員による質疑応答、討論を通して、それらの問題への理解を深めていきます。
▲このページのトップへ
人間環境論演習 IV(H)
森田 茂
- 教育目標
- 障害者のボランティア
- 授業内容
- 人に迷惑を掛けない生き方というものがこれまで大切にされてきたが、障害者の生活はそれでは成り立たない。遠慮なく迷惑を掛けられる社会、安心して援助を依頼できる人間関係を築きたいものである。障害者だから援助される立場を固定すべきでない。ボランティア活動をしている障害者も多く存在し、障害者だから保護されるというのではなく、お互い足りないところを補う関係でありたい。障害や個々の介助の援助を家族や専門家だけのものにせず、ボランティアという形で市民が共に抱え合ってこそ、共生の社会、ノーマライゼーションを実践する社会であると言える。
上記のような社会を実現・発展させるための施策を考えていきたい。
▲このページのトップへ