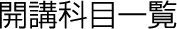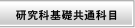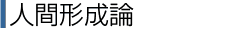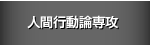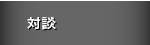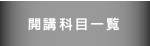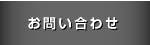人間形成論方法論 I
植村 卍- 教育目標
- 教育と宗教のかかわり
- 授業内容
- 教育も人間にとってひとつの規範である。そうした規範は国家が制定する憲法・法律がそのひとつである。つぎに社会規範として道徳・倫理がある。それは人間が生きる心の規範である。つぎにそうした規範を根本的に規定しているのは宗教である。それはときに潜勢的で目にみえないが、それぞれの国家の文化の根底に潜んでいる。そうした宗教をここではその形態として、たとえばキリスト教・仏教・イスラム教などを研究するものではない。むしろそうした宗教の根底にある 「宗教心」 を研究とする。それは 「聖なるもの」 の研究になる。それはどの民族にも潜んである普遍的な人間の心の性向といえます。
第一回 研究の全貌説明。 第二回 Rudolf Otto の 「聖なるもの」 :オットー著 『聖なるもの』 (岩波書店) 第三回 Hierophanie, Theophanie について 第四回 カオスとコスモスについて 第五回 聖なる時間と神話 第六回 祭の時と祭の構造 第七回 自然の神聖と宇宙的時間 第八回 天の神聖と天上の神々 第九回 遥かなる神 第十回 生の宗教的体得 第十一回 水の象徴 第十二回 女性と産出力 第十三回 総括
人間形成論方法論 II
植村 卍- 教育目標
- 身体論
- 授業内容
- 人間の形成を考えるとき、そこに身体についての思索が必要である。現代の教育を考えるとき、それを学問的に的確に把握しておかなければ、児童・生徒の心を把握できない。ここで研究する身体は、自然科学的な客観的物理的な体ではなく、心と体とが有機的に結合した身体です。こうした身体論は現象学の祖フッサールの哲学において究明された。そして彼の思想に影響されて日本での本格的身体論を展開したのは市川浩である。ここでは、フッサールのそれと、市川の身体論を研究課題とする。
第一回 身体論の全貌とこの講義の計画 第二回 西洋における身体論、デカルトにおける身体論 第三回 拙論 「現象学における身体論」 を中心として(1) 第四回 同上 (2) 第五回 同上 (3) 第六回 同上 (4) 第七回 市川浩 『精神としての身体』 講読 (1) 第八回 同上 (2) 第九回 同上 (3) 第十回 同上 (4) 第十一回 同上 (5) 第十二回 同上 (6) 第十三回 総括
人間形成論特殊講義 I
小松 茂久- 教育目標
- 人間形成と教育制度との関連についての基礎的な概念についての習得をめざす。
- 授業内容
- 実証科学としての教育研究の基本的な考え方のなかでの、 特に制度的アプローチを用いた教育研究の方法を身につけることを目的とする。
教育の科学的研究のプロセスとしての課題発見、 課題明確化、 課題解決に必要な情報の獲得や情報・参考文献等の分析・解釈についての基礎的な手法について学び、 ついで、 研究アプローチとしての歴史的研究、 制度論的研究などについて比較検討することで研究の基本的・基礎的な技術・技法の習得を図る。
これらの研究手法について学ぶとともに、 教育事象の個別具体的課題の解明に取り組む。 研究テーマとしては地域と学校・子どもの問題の解明、 学校・家庭・地域の現代的教育組織化の課題、 学校・家庭・地域の教育機能の意義と課題等など、 受講生の関心に応じて設定する。 特に、 教育制度の形成・変容と教育課題との関連性に留意した研究テーマの設定に留意する。
第1回〜第3回 研究アプローチについて
第4回〜第6回 教育制度論的アプローチについて
第7回〜第9回 教育事象の問題発見・問題解決と研究アプローチの相関性について
第10回〜第13回 レポート作成の技法について
人間形成論特殊講義 II
植村 卍- 教育目標
- 「対話」 の思想----M. Buber; Ich und Du を通しての対話研究。
- 授業内容
- 教育の根幹は 「対話」 でなければならない。教師と児童・生徒の関係は人間的にまず、人格を認め合う対話的存在でなければならない。人間存在を対話的存在として現代初めて確立した M・ブーバーの思想を研究する。そして対話はまた教育指導における重要な方法論でもある。以上な観点から対話思想をここで研究する。
第一回 M. Buber の経歴とその思想・宗教について 第二回 西洋近世のデカルトと哲学の特徴:自意識と真理、自我論について 第三回 近代的自我の限界について。他者存在の先在性にいて。 第四回 M. Buer の“I and Thou”の講読 (1) 第五回 同上 (2) 第六回 同上 (3) 第七回 同上 (4) 第八回 同上 (5) 第九回 同上 (6) 第十回 同上 (7) 第十一回 同上 (8) 第十二回 同上 (9) 第十三回 総括
人間形成論演習 I
前林 清和- 教育目標
- 開発と人間形成
- 授業内容
- 開発教育は、これからわが国の若者たちが自己を形成する際に、必要不可欠な教育になると考える。また、それがわが国が国際社会において一流国として貢献し世界とともに発展していく基礎をつくることになるであろう。
開発教育とは、途上国の文化、歴史を理解しつつ、貧困や紛争、難民問題などをどのように捉え、理解していけばよいのか、またわれわれに何ができるのか、また何をしていくべきなのかということを考えていく教育分野である。
本演習では、世界の現状を把握しつつ、様々な開発教育プログラムを体験し、さらにあらたな開発教育プログラムの開発をおこなっていこうと考えている。
人間形成論演習 II
植村 卍- 教育目標
- 生徒指導と他者 (生徒) 認識----M. Buber の教育論
- 授業内容
- M. Buer の対話思想にもとづいて生徒指導の根本志向を研究する。強制による生徒指導ではなく、共生としての自由教育が彼の基本的な教育論である。他者認識と 「包摂 (Umfassung)、教師の自己陶冶などが具体的なテーマとなる。
第一回 M. Buber の教育論全般について 第二回 拙論 「<生徒指導論>と対話について」 (1992) の講読 (1) 第三回 同上 (2) 第四回 同上 (3) 第五回 同上 (4) 第六回 同上 (5) 第七回 同上 (6) 第八回 同上 (7) 第九回 同上 (8) 第十回 同上 (9) 第十一回 同上 (10) 第十二回 同上 (11) 第十三回 総括
人間形成論演習 III
小松 茂久- 教育目標
- 修士論文作成のための技術と技法について習得する。
- 授業内容
- 教育制度研究、 教育財政研究、 比較教育、 教育史研究などの研究成果を援用しながら、 教育行政研究を中心として、 修士論文の作成のための技術・技能を習得する。 この演習では、 基本的なテキストの解読、 日本教育行政学会編著、 日本教育経営学会編著、 日本教育政策学会編著、 日本教育制度学会編著などに掲載されている諸論文の検討を通して、 教育行政研究の動向と課題についての理解を深め、 受講生の研究テーマの設定と学術論文作成の方法について習得する。
第1回〜第3回 日本教育行政学会と教育行政研究の課題
第4回〜第5回 日本教育経営学会と教育経営研究の課題
第6回〜第8回 日本教育政策学会と教育政策研究の課題
第9回〜第11回 日本教育制度学会と教育制度研究の課題
第11回〜第13回 レポート作成の技法について
人間形成論演習 IV
植村 卍- 教育目標
- 教育と宗教
- 授業内容
- 修士論文完成への道程。 まず宗教一般の本質について、 次に明治憲法下における宗教規定について、 そして最終的に教育と宗教の関連を指導内容とする。
第一回 修士論文提出の日程、 作成などについて
第二回 宗教一般の本質について エリア-デを中心として
第三回 宗教一般の本質について オットーを中心として
第四回 明治憲法下における宗教の取り扱いについて①
第五回 明治憲法下における宗教の取り扱いについて②
第六回 戦後の憲法下における宗教の取り扱いについて①
第七回 戦後の憲法下における宗教の取り扱いについて②
第八回 戦後の憲法下における宗教の取り扱いについて③
第九回 戦後の憲法下における宗教の取り扱いについて④
第十回 道徳教育と宗教について
第十一回 社会教育と宗教について①
第十二回 社会教育と宗教について②
第十三回 総 括