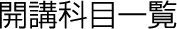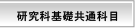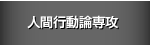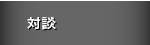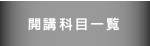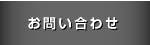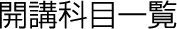

人間環境論ワークショップ
鹿島 基彦
- 教育目標
- 南からやってくる黒潮、 対馬暖流、 津軽暖流、 宗谷暖流などの暖流、 北からやってくる親潮などの寒流、 海の高速道路として機能してきた瀬戸内海、 これらの海流と海陸地形は、 日本の気候・植生・民族の分布と物流に大きな影響を与えてきた。 したがって、 日本の民俗学を考える上で、 海からの影響はとても大きい。 この演習では、 日本の海と民俗学の関係について考察していく。
- 授業内容
第1回 自己紹介とゼミの基調方針
第2回 各自の研究題材の決定
第3-9回 文献検索と議論
第10-12回 研究結果発表
第13回 総括討論
▲このページのトップへ
心理学ワークショップⅠ
吉野 絹子
- 教育目標
- 私たちの身の回りにあるリスクを考える。 便利さの中に潜むリスクをどのように評価し、 マネジメントするかについて、 さまざまな事例に基づいて検討し、 理解を深める。 /dd>
- 授業内容
- 私たちの 「便利で快適な生活」 は、 科学技術の成果に負うところが大きい。 しかし、 このような 「快適さや便利さ」 は、 いつも何らかのリスクと隣り合わせになっているのも事実である。 このような身の回りのリスクに関する情報を、 どのように管理し、 どのようにリスクコミュニケーションしていくかについて、 検討を加える。 輪番で担当部分をまとめて報告し、 参加者の相互討論をおこなう。
第1回:はじめに
第2回:環境リスクのアセスメントとリスク心理学の役割
第3回:確率と結果の認知
第4回:確率と結果の認知
第5回:リスク2成分とリスク削減要求
第6回:リスク2成分とリスク削減要求
第7回:人々はゼロリスクをもとめるか
第8回:人々はゼロリスクをもとめるか
第9回:探索型リスク認知研究
第10回:探索型リスク認知研究の問題点
第11回:心理的構成重視のリスク認知
第12回:心理的構成重視のリスク認知
第13回:リスク概念再考
第14回:信頼の重要性
第15回:まとめ
▲このページのトップへ
心理学ワークショップⅡ
山上 榮子
- 教育目標
- ・アートセラピーの理論と実践の習得
- 授業内容
- アーツセラピー (芸術療法) のひとつであるアートセラピーは、 描画、 コラージュ、 粘土による造形など、 視覚芸術領域を通しての自己表現によるセラピーです。 葛藤が問題化している臨床群はもちろん、 こどもや高齢者、 発達障害児 (者) の理解と援助のために有効な非言語的アプローチです。 本ワークショップでは、 イギリス・アートセラピーの理論と方法論に基き、 日本での医療、 教育、 福祉などの諸領域で適用できることを目指します。 グループ・ベイストの体験的トレーニングですので、 他メンバーとかかわることを承知の上で参加してください。
第1回:オリエンテーション (グループ編成とルールの確認)
第2回:ひとりでのワーク (テーマを決めて)
第3回:ひとりでのワーク (自由に)
第4回:ペアでのワーク (テーマを決めて)
第5回:ペアでのワーク (自由に)
第6回:グループでのワーク (テーマを決めて)
第7回:グループでのワーク (自由に)
第8回: (グループ再編成) ひとりでのワーク (テーマを決めて)
第9回:ひとりでのワーク (自由に)
第10回:ペアでのワーク (テーマを決めて)
第11回:ペアでのワーク (自由に)
第12回:グループでのワーク (テーマを決めて)
第13回:まとめ
▲このページのトップへ
人間形成論ワークショップ
前林 清和
- 教育目標
- 人間形成論の視野の拡大とポイント
- 授業内容
人間形成論の研究範囲は広範囲に及び、 またどのような視点で人間をとらえるか、 人生をとらえるかによって人間形成のあるべき姿は大幅に変わることになる。
混迷の21世紀、 今までの人間観や人生観、 価値観は通用しなくなっている。 これから、 如何に生きるか、 そのためにはどのような人間形成が望まれるのかということを真剣に問い直す時期にきているのではないだろうか。
本ワークショップでは、 「私」 をどうとらえ、 私に関わる社会や国家、 世界をどのように捉えることができるのか、 ということを多面的に考えていきたい。
そのための方法として、 下記の活動をしながら、 それをもとに討論していきたい。
①自分自身を知るための作業や検査をおこなったり、 家族や人間関係について調査する。
②社会や世界との関わりを考えるための講演会を聴講したり映像を見たり、 作業を行なったりする。
③学外の教育、 国際協力、 ボランティア関連の施設で研修を行う。
▲このページのトップへ
社会構造論ワークショップ
早木 仁成
- 教育目標
- 野外調査を体験する
- 授業内容
- 人類学の基礎をなす野外調査においては、 人間や霊長類の行動を直接観察するほか、 写真撮影、 録音、 ビデオ撮影、 動植物標本の作製、 インフォーマントへのインタビュー、 アンケート調査などを行わなければならない。 また、 そのようにして得られた資料は、 研究室に帰ってデータ処理をされなければならない。
本ワークショップでは、 主として野外での実習を通して、 このような野外調査における必須の技術を身につけさせ、 十分なフィールドワークの基礎作りを指導する。
▲このページのトップへ
社会関係論ワークショップ
春日 雅司
- 教育目標
- ここではイギリスの社会学者、 アンソニー・ギディンスが学部学生向けに書いた 『社会学』 というテキストを使いながら、 現代社会学の基礎を学びます。 この著書は初版が出た時から大変大部なもので、 内容的には平易に書かれているのですが、 その分厚さゆえに手にすることがためらわれるものでした。 授業ではそのごく一部しか読めませんが、 邦訳でいいからがまんしてじっくり読み終えると、 みなさんにも社会学のおもしろさが理解していただけるのではないかと思いますので、 ぜひ図書館で借りるなりして読んでみてください。 この授業で英文を取り上げる目的ですが、 その一つのねらいは、 社会学がどういう問題をどういう方法で現代社会の諸問題解決のために取り組んでいるのかを理解すること、 もう一つのねらいは受講生の論理力・思考力を高めることです。 みなさんは、 いずれ日本語で論文を書くわけですが、 外国語を読むことで、 分かっていると思っている日本語が実は分かっていなかったということを知るようになります。 よりよい日本語を使うことは重要ですので、 この授業はそのための第一歩だと思ってください。 一字一句、 そして基本タームをきちんと理解すると同時に全体として何かが書いてあるのかを理解するようにつとめてください。
授業は輪読形式で進めます。 出席者の誰がどのように分担していくかは、 受講生と相談の上決めます。
なお、 1989年に出た原著は改版の度に大きな変更を加えられています。 日本語訳もあり、 原著の改版の度に改訳されていますが、 第5版については未だ邦訳されていません。 この授業では原著の第1章を読みます。 第4版と同一の部分もありますが、 手直しされている部分もあります。 ここでは、 改版の経緯について深入りしませんが、 授業計画に示した項目は第4版の目次にもとづいたものであり、 第5版のものとは違うことをお断りしておきます。
- 授業内容
1. Studying sociology
2. Awareness of cultural differences
3. Assessing of the effects of policies
4. Self-enlightenment
5. Early theorist
6. Auguste Comte
7. mile Durkheim
8. Karl Marx
9. Max Weber
10. Functionalism
11. Conflict perspectives
12. Symbolic interactionism
13. Summary points
▲このページのトップへ
文化構造論ワークショップ
竹田 賢治
- 教育目標
- ドイツ語訳、 松尾芭蕉 『奥の細道』 を読む
- 授業内容
- 海外での日本俳句の研究はすでに百年の歴史をもっている。 とりわけ、 芭蕉の 『奥の細道』 は多くの外国語に翻訳されているが、 ドイツでは1985年に G. S. ドムラディによる名訳が出版された。 授業では芭蕉の原文と対照しながら読んでいく。 季語、 歌枕、 切れ字はどのように処理されているか。 5・7・5のリズムはどうなっているか。 何よりも世界でもっとも短い詩とされる俳句は、 そもそも詩として理解されているのか。 これらのことを検討しながら、 外国における日本文化受容のひとつの具体例を吟味し、 比較文化への手がかりをみつけたい。
▲このページのトップへ
芸術文化論ワークショップⅠ
伊藤 茂
- 教育目標
- 上演批評を書く
- 授業内容
- 演劇において上演批評とか劇評とか言われる文章は、 観客の感想を代表するものとして貴重な資料になりうる。 もちろん批評にもさまざまなレベルがありうる。 この授業では、 実際に上演批評を書いてもらい、 よりよい批評文とはどのようなものかを考えていく。 そのための前提として、 しばしば劇場に行き演劇を鑑賞することは必須の作業 (義務) となる。
▲このページのトップへ
芸術文化論ワークショップⅡ
桑島 紳二
- 教育目標
- 情報社会における情報発信の作法を修得する。
- 授業内容
- 数年前より出版業界では、 若者や女性をターゲットにした学術系新書の創刊が相次ぎ、 人気を集めている。 活字離れによる出版不況の中、 身近な内容の新書を次々投入し、 新たな読者を引きつけている。 こういう現象を 「知のコンビニ化」 と称して眉をひそめるひともいるが、 ケータイで忙しい若者たちが新書をきっかけとして読書習慣がつくのであれば意義のあることである。
ところで、 新書ブームを出版サイドから見れば、 売れる企画や書き手がなかなか見つからないという状況にある。 つまり本を著すことはわれわれが思っているほど敷居は高くない。 ただし、 企画がおもしろければの話だが。
そこでこの授業では、 新書向きの持ち込み企画を立てて実際に出版社にアプローチする。 そういうプロセスを経験することで、 情報発信の作法を実戦で身につけよう──というのがこの講義の狙いである。
専門分野での研究内容をそのまま世間に発信してもウケない。 興味深いけれど研究とは直接関係ない情報が意外にウケるかもしれない。 そのような自分が今まで貯めこんできた知識を、 社会という視点で見直して棚卸ししてみる。
情報社会である現代、 研究者の道を歩むにせよ、 社会で働くにせよ、 世の中に向けて情報発信していく作法を身につけておくことに損はない。 また、 企画が評価され出版への道が開けるかもしれない。
▲このページのトップへ
言語文化論ワークショップⅠ
野田 春美
- 教育目標
- 論理的な文章を書くための文章表現力を身につける
- 授業内容
- 修士論文執筆の前段階として、 論理的な文章を書くための実践的なトレーニングを行う。 自分の考えを人に伝えるというのはどういうことか、 構成を整え、 読みやすい流れを作るというのはどういうことか、 体験しながら学んでほしい。
第1回 文章表現力の確認 (テスト形式)
第2回 課題文1の構想 (執筆は次回までの宿題とする)
第3回 課題文1の相互コメント (改稿は次回までの宿題とする)
第4回 課題文1改訂版の相互コメント、 完成
第5回 課題文2の構想 (執筆は次回までの宿題とする)
第6回 課題文2の相互コメント (改稿は次回までの宿題とする)
第7回 課題文2改訂版の相互コメント、 完成
第8回 課題文3の構想 (執筆は次回までの宿題とする)
第9回 課題文3の相互コメント (改稿は次回までの宿題とする)
第10回 課題文3改訂版の相互コメント、 完成
第11回 期末レポートの構想 (草稿執筆は次々回までの宿題とする)
第12回 まとめ
第13回 期末レポート草稿の相互コメント (改稿したものが期末レポートとなる)
▲このページのトップへ
言語文化論ワークショップⅡ
熊田 俊二
- 教育目標
- ことばと文化の諸相
- 授業内容
- 実例の言語分析を実際に行いながら、 視野を広げるための体験的学習をしたい。 例えば、 日本語を世界の諸言語の中の1つの言語として分析した場合、 どのような特徴と傾向を持った言語なのかを垣間見ることが出来るのではないだろうか。 さまざまな言語データを観察しながら、 その言語の特徴を整理し、 分析のプロセスを通して、 各言語を支える文化・発想の特異性と普遍性、 さらには一般に言語とはどのようなものなのか、 などを考えてみたいと思う。
▲このページのトップへ
表現言語論ワークショップⅠ
植村 眞知子
- 教育目標
- 王朝貴族の人間像を探る
- 授業内容
- 『大鏡』 を取り上げる。 『大鏡』 は、 平安時代の王朝貴族たちの実像・虚像を取り混ぜた逸話を多く伝えている。 その中で、 実在の人物たちの、 実像としての人間像をどのように捉えていくか、 傍証史料と照らし合わせながら丁寧に本文を読むことから考えてみたい。 前期に 「表現言語論方法論Ⅰ (J)」 を履修していることが望ましい。 前期に行った傍証史料の取り扱い方を参考にして、 本文の担当箇所を各自でできるだけ綿密に調べ上げ、 その読解を発表してもらうことで授業をすすめていく。 本文の流れに従って読みすすめるが、 今年度は 「公季伝」 を取り上げる。
▲このページのトップへ
表現言語論ワークショップⅡ
久保田 重芳
- 教育目標
- イギリスの小説家 D.H.ロレンスの文学論 (英文) を読み、 そこに提示されている 「芸術とモラル」 の問題について理解を深めたいと思います。
- 授業内容
- テキストを輪読します。 一人一ページ程度の英文についてよく調べ、 その内容についてよく理解したうえで、 何が問題となっているのかを確認し、 議論します。
言うまでもありませんが、 読むことは正確な一語一語の発音からテキストに内包されているメッセージにいたるまでのすべてを取り込むことを意味します。 そのためには、 読み手側の受容の態勢が周到でなければなりません。 テキストに対する準備や予習などが、 コンスタントに行われることを前提に、 授業を行いたいと考えています。
▲このページのトップへ
表現言語論ワークショップⅢ
南森 孚
- 教育目標
- トーマス・マンの自伝的作品を手がかりにして、 作家の人生と小説の成立との係わりについて考察していく。
- 授業内容
- トーマス・マンは1929年にノーベル文学賞を受賞しているが、 この受賞を切っ掛けに、 その半生を綴った自伝的随想 「Lebensabrβ」 (『略伝』) を書き上げている。 この作品の中から、 小説家の人生とその諸作品との係わりについて読みとっていく。 またその中でゲーテの 「Dichtung und Wahrheit」 (『詩と真実』) についても言及しており、 ゲーテについても考察していく。
歴史情報論ワークショップ
植田 俊郎
- 教育目標
- フランス革命における議会への報告書の数量分析の方法の習得
- 授業内容
- フランス革命期の国民公会への地方からの報告書 (意見書) を計量的に分析することによって、ジャコバン独裁の構造と変容を理解する。そのために、先ずミシェル・ヴァヴェルの研究および 『フランス革命の図表』 における典型例をとりあげ、計量分析の方法と成果を理解する。そして国民公会の議事録から共和暦第二年ヴァントーズの所謂コルドリエ (またエベール) 派の蜂起に関する地方の民衆協会からの報告書を抽出し、地域ごとに、蜂起への賛否、記載人物名などの項目毎に分類し、それらを数量的に分析し図表化する。最後に、図表化された歴史情報からジャコバン独裁の意味、つまりその構造と変容を探る。
▲このページのトップへ
情報処理ワークショップ I
上椙 英之
- 教育目標
- データベースの理解と構築、 運用の習熟践
- 授業内容
- データベースという言葉は、 狭義には、 「特定の目的に応じて大量のデータを集めたもの」 というデータ部分だけを指すが、 広義には、 「管理・検索するソフトウェア (データベースシステム)」 を指す。 データベースの活用方法の一つには、 図書館の蔵書検索やインターネットでの Web 検索に代表される、 「他人が準備してくれたデータベースを利用する」 という方法が挙げられる。 もう一つの活用方法には、 自分が所有する CD や書籍の一覧表をつくったり、 住所録をつくったりするという 「自分の情報整理のためにデータベースにする」 という方法がある。 このワークショップでは、 後者の 「自分の情報処理のためのデータベース」 の構築を目指す。
Microsoft Access を使い、 先ずは、 利用する目的に応じたデータ構造の設計から、 データの入力、 条件による検索、 様々な形式での出力という活動をおこない、 データベースの仕組みを理解し、 データベース構築の方法の習得を目指す。 その後、 構築したデータベースを使い、 必要な情報の抽出、 論理演算の理解、 データの型に合わせた条件式の入力、 複数に構築されたデータベース上の関連データの結合などのデータベースの運用の習熟を目指す。
▲このページのトップへ
情報処理ワークショップ II
上椙 英之
- 教育目標
- データの解析と発信の習熟
- 授業内容
- 「情報処理ワークショップⅠ」 では、 データベースの構築に主眼を置くが、 「情報処理ワークショップⅡ」 では、 データの解析に主眼を置く。
統計ソフトの SPSS や Excel を用いて、 効果的な図表や簡単な統計解析の手法を学ぶ。 収集したデータを用いた効果的な図表の作成や、 それらの図表を用いて議論を進めていくことは、 研究を続ける上で必須の技術と言える。
先ずは、 Excel を用いて図表作成・統計解析の基礎技術の習熟を目指す。 なお、 各自の習熟度によっては、 SPSS を用い、 より効果的なデータの解析について学んでいく。
▲このページのトップへ
英語論文作成ワークショップ I
グリーサマー, M
- 教育目標
- Classmates working together in pairs and groups, students learn to enjoy writing as a process of creation, collaboration and revision.
The teacher will expect : i. good attendance, ii. enthusiastic participation in class iii. regular preparation of homework assignments.
- 授業内容
- 1. Course rules / Introduction
2. Greeting / Classroom English
3. Getting Acquainted-writing about someone in class
4. Parts of a Paragraph
5. Review Punctuation and use of capital letters
6. Practice taking notes-vocabulary use.
7. Unity and Coherence
8. Writing about someone you admire
9. Peer check
10.Brainstorming and Outlining
11.Opinion letter
12.Edit your writing
13.Open day
14.Final presentation
▲このページのトップへ